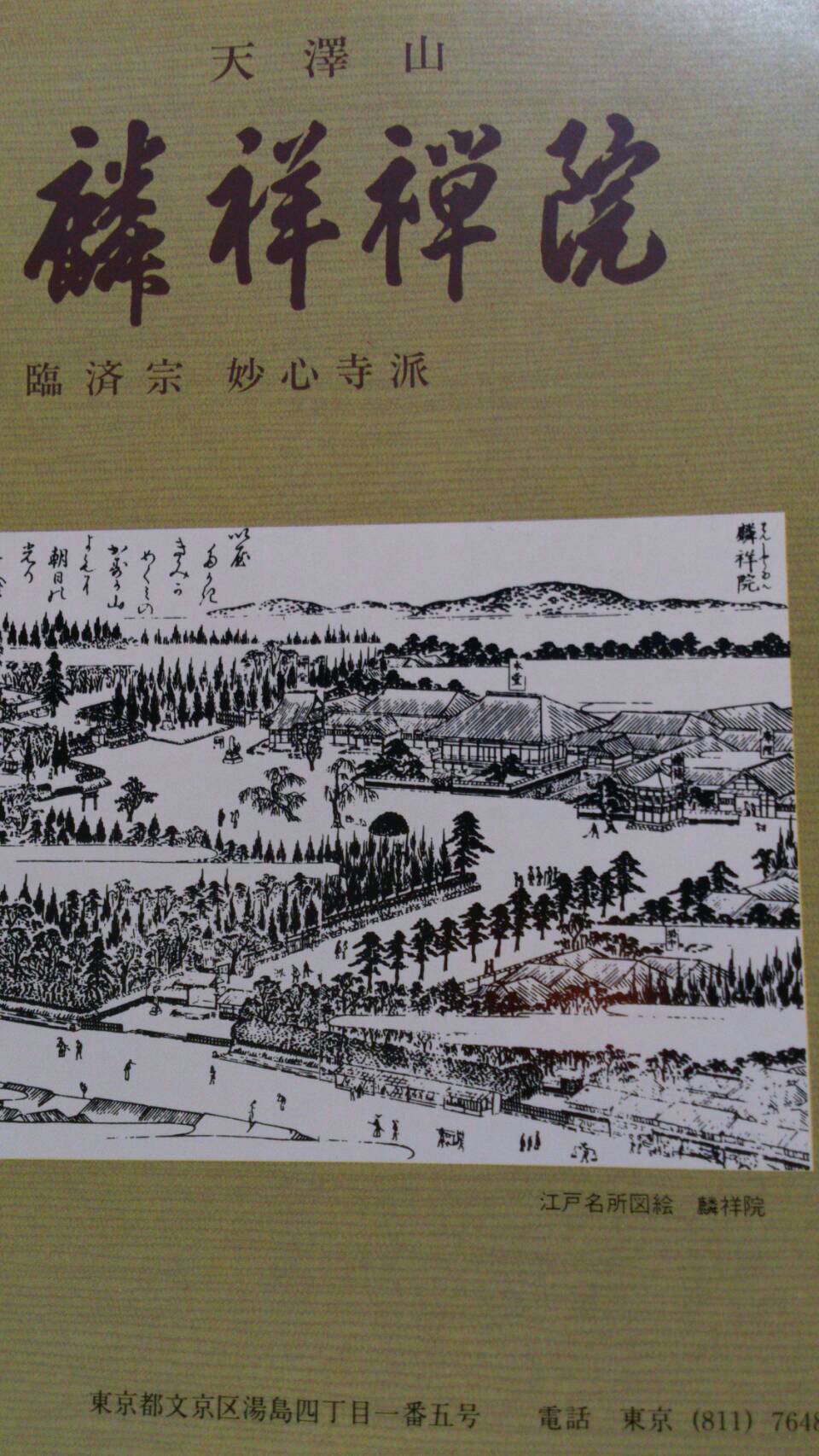会員のカネコです。
昨年末、ロシアのプーチン大統領来日でにわかに北方領土が注目を浴びましたが、北方四島をはじめ、樺太・千島列島が日本の領土になった経緯というものはもう一度理解するべきなのではないかと思いました。
その中で出会ったのが今回紹介する初代蝦夷奉行羽太(はぶと)安芸守正養です。
江戸後期から明治にかけて様々な人物が北海道から周辺の島々を命がけで探険し、その土地に住む人々や風土を調査したことにより、未知の世界であったこの地域の実情が明らかになりました。例えば伊能忠敬や間宮林蔵などはその代表的な人物です。
今回紹介する羽太安芸守正養は地味な存在ではありますが、旗本で蝦夷地奉行、箱館奉行、松前奉行を歴任し、現在の北海道千歳市の「千歳」の命名者といわれている人物です。
『寛政重修諸家譜』によると正養は羽太勘兵衛正香の子で、通称を庄左衛門といい、御蔵奉行、田安家の用人、御目付などを歴任しています。寛政譜の記載はここまでですが、『徳川幕臣人名辞典』によると、享和2年2月23日(1802・3・26)に蝦夷奉行、同年5月10日(1802・6・9)に箱館奉行(文化4年10月24日(1807・11・23)に松前奉行と改称)となっており、まだ未開の地であった蝦夷地の行政や警固の任にあたっています。
正養の蝦夷地での業績については大塚武松著「追録 箱館奉行羽太正養と蝦夷地経営」(『幕末外交史の研究 』)、北海道総務部行政資料室編 『開拓の群像 中巻』に詳しく書かれています。
寛政11年(1799)幕府は南下政策を進めるロシアを警戒し、東蝦夷地を松前藩から引きあげ、直轄地としました。そして蝦夷地取締御用掛を新設し正養のほか、松平信濃守忠明・石川忠房・大河内政寿・三橋成方を任じました。
蝦夷地取締御用掛として箱館に赴いた正養は、箱館に造船場を建設し、通行の便を良くするため、堀を作り、そこに橋をかけ栄国橋と名付けました。
また、当時は渡航が危険であったクナシリ島(北方領土の国後島)へ渡航し、島の隅々まで検分を行いました。
飲み水が悪く困っていたトリマでは重松という従者に命じて井戸を掘らせた所、質の良い水が沸きだし、正養はこれを「重松の井」と命名し、次のような歌を詠いました。
「いく世々にくみて知るらむつくりなす 坂井の水のふかきめぐみを」
箱館に戻った正養は江戸に帰り詳細な、検分記録と地図を幕府に提出しました。
共に蝦夷地御用取締掛を務めた松平信濃守忠明とは深い友情で結ばれており、『開拓の群像 中』には次のようなエピソードが記されています。
正養は駿府城代に昇進した忠明に手紙を送って、忠明の敏腕を褒めながらも、はやる心をおさえて、おもむろに進むこともまた必要であると忠告をしています。これに対し忠明は「兄のことばのようにありがたくいただく」と答え「このごろのエトロフの発展をもって忠明の手柄のように評判する向きもあるが、これはみな、あなたのおかげである。この間も将軍家へそのように申し上げました」と功を譲り合い、ともに失敗のないよう戒め合いました。
また、ある年、正養が箱館へ赴く時、忠明は「何か贈り物をしたが、何が欲しい」と尋ね、正養は「奉行所勤務のひまひまに使いたいから、蹴鞠が欲しいのだが、手に入るかどうか」と返事をすると、忠明は蹴鞠を八方探し求め正養に送りました。
遠く離れた蝦夷の地で友を想いながら、蹴鞠に興じる正養の姿が目に浮かぶようです。
蝦夷地取締御用掛として功績を挙げた正養は享和2年2月23日(1802・3・26)戸川筑前守安論(宝暦12年(1762)~文政4年3月23日(1821・4・25)曲直瀬正山の二男)と共に初代蝦夷奉行に任じられ、交代で箱館に在勤しました。
正養と戸川は拡大された幕府直轄地への新政の確立と経費を定めることで、松前藩時代の悪弊が改められ、北方経営は順調に進展しました。また、両名は蝦夷地に三寺を新設し、箱館近辺の開墾、虻田に牧場を開設するなど、業績を挙げていきました。
文化2年(1805)には当時シコツと呼ばれていた千歳地方を訪れ、シコツ川を千歳川と改名し、このことにより「千歳の名付け親」とも呼ばれています。
順調に進んでいたかに思われた蝦夷地経営は文化4年(1807)に暗転することになります。
この年の4月29日(1807・6・5)ロシア船2艘がエトロフ島(北方領土の択捉島)ナイボ(内保)を襲撃し、さらに幕府の会所があったシャナ(紗那)を襲撃しました。会所を守っていた戸田亦太夫は詰めていた南部・津軽各藩の兵に命じ、上陸してきたロシア水平と一戦を交えましたが、陣屋は火器に劣り敗れ、夜に会所を焼き払い退却。その途中亦太夫はアリモエで責を負って自刃。亦太夫は寛政11年(1799)蝦夷地取締御用掛が新設された際に普請役として蝦夷地に赴いて以降、蝦夷行政に携わっており、志半ばにしての無念の最期でありました。
この事件の際、測量で訪れていた間宮林蔵は会所を打って出る主戦論を唱え奮戦、高田屋嘉兵衛の漁場の支配人川口寅吉も負傷しています。
この事件が正養のもとに届いたのが翌5月になってからで、正養は幕府に急報し、南部・津軽両藩の出動を促しました。7月に江戸から幕兵を連れて箱館に来た若年寄堀田正敦は蝦夷地を検分し、正養の治績が上がっていることを認めたものの、エトロフの敗戦の責は正養にあるとして、10月に江戸に戻され、戸川安論とともに奉行職を解かれ、小普請逼塞を命じられました。逼塞は翌年に解かれましたが、彼が再び表舞台に出ることはなく、文化11年1月22日(1814・3・13)62歳で没しました。
正養の大きな功績は『休明光記』を書き残したことです。
在任中の蝦夷地の行政をはじめ、松平忠明・戸川安論・最上徳内・近藤重蔵・高田屋嘉兵衛など、共に蝦夷で働いた仲間の事績も書かれており、本編9巻、その参考となる文書類を集めた附録11巻、附録一件物3巻、附録別録4巻の計27巻からなる大著となっています。これは幕府の蝦夷地行政を知る一級資料となっています。
『休明光記』は函館市中央図書館所蔵デジタルアーカイブで閲覧することができます。
『休明光記』
正養は元来蒲柳の質であったといい、幼い頃より心を文に寄せ、和漢の書に通じ、よく歌や句を詠みました。また、『羽太氏家訓』を遺し、忠孝五倫の大義より、父子・夫妻・主従・長幼の関係、学問の選択、日常細末の心得を古今和漢の例証に照らして書いています。
正養の墓は私の自宅から近い品川区南品川2丁目8-23の顕本法華宗別格山天妙国寺にあります。
『寛政重修諸家譜』によるとこの天妙国寺は羽太家3家が菩提寺としています。
羽太家は藤原氏利仁流を称し、徳川家康に仕えた羽太半蔵正次にはじまります。
正次は天正18年(1590)家康が関東へ移った際に従ったものの病のため三河国額田郡大門村に隠遁し、その子正俊は慶長2年(1597)29歳で早世、その子正成は祖父の許で養われ大門村で育ちました。慶長19年(1914)家康が大坂冬の陣へ向かう途中、正成は供奉する事を願い出て、大樹寺の門前で家康の御前に召され、姓名を尋ねられました。すると正成は家康の側に仕える事を命じられ供奉の列し、大坂夏の陣にも側で仕え、その後、駿府において近習を務めてました。家康死去後、大番となり、甲斐国八代郡のうちに150石を賜りました。
この正成には男子が多く、二男勘兵衛正弘は甲府宰相綱重の附属して桜田館の小性組を務め、後に綱重の子綱豊が将軍綱吉の世子家宣として西の丸に入ると幕臣となり300俵を賜っています。
三男庄左衛門正平も同じく甲府宰相綱重の小性から家宣に従い幕臣となり500俵を賜った家であり、この正平が正養の祖であり、正養は正平から数えて5代目となります。
尚、当会幹事のカトケンさんのご先祖も桜田館に出仕しており、羽太正弘・正平とは同僚であったことになります。
以上の本家・正弘家・正平家の3家が天妙国寺を菩提寺としており、正成五男清左衛門正次の家は四谷松岸寺を菩提寺としています。
正平家の墓は合葬墓となっており、正面に[羽太家累世之墓]と刻まれ、3面には撰文が刻まれており、享和3年(1803)正養によって建立された墓碑であることが分かりました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]() Image may be NSFW.
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
この墓は私が北品川に転居して間もない平成24年(2012)1月に初めて訪れ撮影しました。
この時のことは以前のブログにも書いています。
品川宿の寺々
その後、数度訪れていましたが、昨年末に訪れた際、京急本線ガード下付近の無縁集石地に移動されていました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
後継者が絶えたためだと思われますが、昨今各地で無縁墓が廃棄される中で、このような形で保存されたことにお寺側の心遣いを感じました。
正弘家の墓所は墓地左最奥にあり、歴代の墓が良好な形で残されています。
また、本家の墓は今まで見つけることが出来ませんでしたが、昨年末の調査で、無縁集石墓に移された正平家の墓の左隣の小さい墓碑の側面に[羽太清右衛門]と刻まれてあるのを見つけ、清右衛門とは本家の当主の通称であることから、これが本家の墓であったことが分かりました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
平成24年(2012)に訪れた際は正養の人物像については全く知りませんでしたが、昨年のプーチン大統領来日で北方領土の歴史を調べた中で、この羽太正養の名が出てきて、天妙国寺で見た墓と繋がりました。
そこから見えたのは当時未開の地であった蝦夷地の発展に半生を掛けた一人の男の生涯と、命をかけて蝦夷地で生きた仲間達の姿でありました。